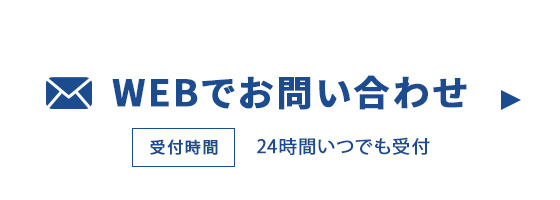相続財産とは、被相続人(亡くなった方)が残した全ての財産を指します。これには、プラスの財産だけでなく、負債といったマイナスの財産も含まれます。
相続財産を正確に把握することは、相続手続きを円滑に進めるために非常に重要です。
この記事では、相続財産の具体的な種類と、それぞれの特徴について詳しく説明します。
相続財産に当てはまるもの
以下は、相続財産に当てはまるものの具体例です。
- 不動産…土地、建物
- 預貯金…普通預金、定期預金、外貨預金
- 有価証券…株式、債券、投資信託
- 動産…自動車、宝石、骨董品など
- 保険金…生命保険金
- その他…知的財産権(著作権など)、未収金
不動産
土地:住宅用地、事業用地、農地など。
建物:住宅、商業施設、賃貸物件など。
具体例:東京都内にある自宅、郊外に所有する別荘、事業用のオフィスビル。土地や建物は相続財産の中でも大きな割合を占めることが多く、相続手続きには登記の変更が必要です。
預貯金
普通預金:日常的に使用する銀行口座の残高。
定期預金:一定期間引き出しができない預金。
外貨預金:外国通貨で預けられている預金。
具体例:三菱UFJ銀行の普通預金口座、三井住友銀行の定期預金口座。預貯金は各金融機関で相続手続きが必要です。
有価証券
株式:上場株式、非上場株式。
債券:国債、社債。
投資信託:投資信託口座に預けられた資産。
具体例:トヨタ自動車の株式、政府発行の国債、野村證券の投資信託。株式や債券は証券会社での手続きが必要です。
動産
自動車:被相続人が所有する車。
宝石・貴金属:指輪、ネックレス、金貨など。
骨董品・美術品:絵画、彫刻、古文書など。
具体例:メルセデス・ベンツの車、ダイヤモンドリング、ピカソの絵画。動産は相続財産として評価され、相続手続きが行われます。
保険金
生命保険金:被相続人の死亡により支払われる保険金。
具体例:生命保険契約による死亡保険金。生命保険金は「500万円 × 法定相続人の数」まで非課税です。
その他の財産
知的財産権:著作権、特許権など。
未収金:貸付金、売掛金など。
具体例:著書の著作権、特許取得済みの発明、友人に貸しているお金。知的財産権や未収金も相続財産に含まれます。
相続財産に当てはまらないもの
相続財産には含まれないものもあります。これらの財産は、相続人が引き継ぐことができないため、注意が必要です。
生命保険の受取金(特定の条件下)
生命保険の受取人が相続人以外の個人である場合、その保険金は受取人の固有財産となり、相続財産には含まれません。
具体例:被相続人が生命保険の受取人を友人に指定していた場合、その友人が受け取る保険金は相続財産に含まれません。
退職金の死亡退職金
死亡退職金も特定の受取人が指定されている場合、その受取人の固有財産となり、相続財産には含まれません。
具体例:被相続人の会社から支給される死亡退職金が指定の受取人に支払われる場合、その受取人の固有財産となります。
公共年金
被相続人が受け取っていた公共年金(厚生年金、国民年金など)は、被相続人の死亡により支給が停止されるため、相続財産には含まれません。
具体例:被相続人が生前受け取っていた国民年金の支給は死亡と同時に停止されるため、相続財産には含まれません。
個人的な権利義務
被相続人の個人的な権利や義務(扶養義務、使用借権、生活保護受給権など)は、相続財産には含まれません。
具体例:被相続人が生前に受けていた生活保護受給権や、他人から借りていたものの使用借権。
みなし相続財産と生前贈与財産に注意!
相続財産には含まれないものでも、相続税の計算上は相続財産とみなされる「みなし相続財産」と、相続開始前に贈与された財産で特定の条件下で相続税の課税対象となる「生前贈与財産」があります。
みなし相続財産
みなし相続財産とは、被相続人が死亡したことによって初めて相続人が受け取ることができる財産を指します。具体的には以下のようなものがあります。
生命保険金
被相続人が契約者で、保険金の受取人が相続人の場合、生命保険金は「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。ただし、500万円×法定相続人の数まで非課税となります。
死亡退職金
死亡退職金は受取人の固有財産になると説明しましたが、被相続人が死亡したことで発生するものであることから、実質は相続財産と変わらないため「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。ただし、これも一定の非課税枠が適用されます。
生前贈与財産
被相続人が相続開始前3年以内に贈与した財産は、相続税の課税対象となります。これを「生前贈与財産」と呼びます。生前贈与により相続財産を減少させることで相続税の支払いを逃れようとするのを防ぐためです。
相続財産の確認方法
相続財産を正確に把握することは、相続手続きを円滑に進めるために非常に重要です。
以下に、相続財産の確認方法を具体的に説明します。
不動産の確認方法
不動産は、登記事項証明書を取得することで確認できます。登記事項証明書には、土地や建物の所在地、所有者、面積、権利関係などが記載されています。
預貯金の確認方法
預貯金の確認には、被相続人が利用していた金融機関に問い合わせることが必要です。各金融機関から預貯金の残高証明書を取得します。
有価証券の確認方法
有価証券の確認には、証券会社に問い合わせて被相続人が保有する株式、債券、投資信託などの明細を取得する必要があります。また、株式や債券については証券会社の取引報告書や残高証明書を確認します。
動産の確認方法
動産の確認には、被相続人が所有する財産のリストを作成し、それぞれの市場価値を評価する必要があります。自動車については車検証、宝石や貴金属については鑑定書や購入時の領収書、骨董品や美術品については専門家の鑑定を受けます。
保険金の確認方法
保険金の確認には、生命保険会社に連絡し、被相続人が契約者である保険契約の内容を確認します。保険証券や契約書をもとに、保険金の額や受取人を確認します。
その他の財産の確認方法
知的財産権や未収金の確認には、それぞれの契約書や権利証書、請求書を確認します。著作権や特許権については、特許庁のデータベースや契約書を確認し、未収金については貸付金や売掛金の契約書を確認します。
まとめ
相続財産には、不動産、預貯金、有価証券、動産、保険金、その他の財産が含まれますが、生命保険の受取金や死亡退職金、公共年金などは相続財産に含まれません。また、みなし相続財産や生前贈与財産も相続税の課税対象となるため、注意が必要です。
相続財産を正確に把握し、適切に評価することは、相続手続きを円滑に進めるために非常に重要です。相続財産の確認方法を理解し、専門家の助言を受けながら、スムーズな相続手続きを実現しましょう。具体的な財産の確認方法を実践し、相続人全員が納得できる形で遺産分割を行うことが望まれます。
司法書士法人アクセス総合事務所では、相続に関する幅広い相談に対応しています。相続財産の確認方法から遺産分割の進め方、相続税対策まで丁寧にサポートいたします。複雑な相続の問題も、お気軽にご相談ください。