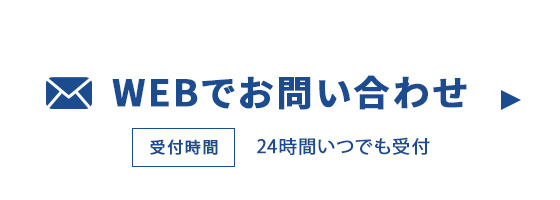遺言
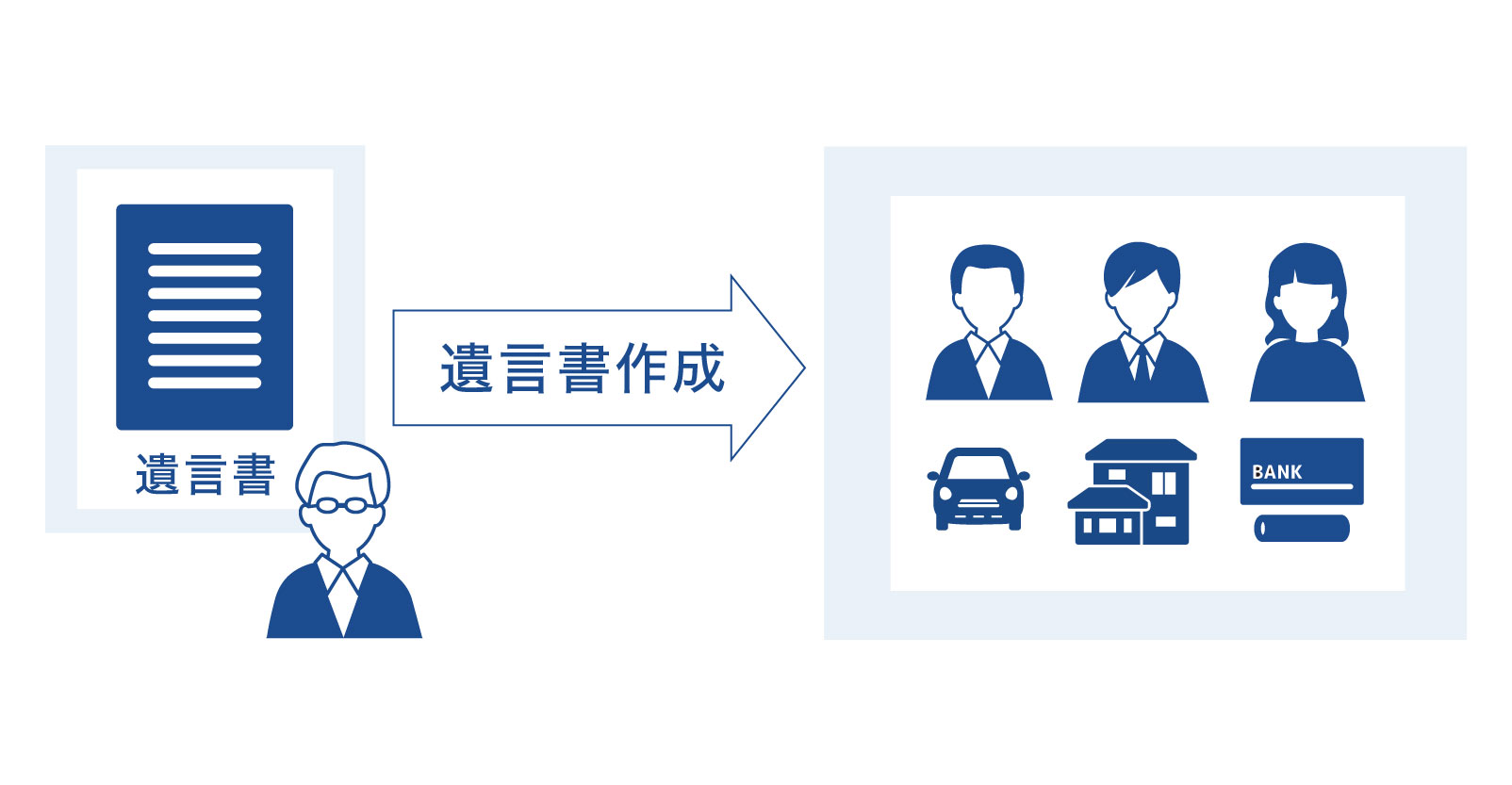
自分が亡くなった後に身内で遺産を巡って争いになることは誰しも望んでいないと思います。
相続人同士が争う「争族」とならないためには、自分の意思を生前に遺言として残しておくことが一番です。
遺言(いごん・ゆいごん)とは亡くなった方の最後の意思表示ですが、一般的には「家族仲良く暮らすように」とか「子供たちは母親を大切にするように」というような内容を言い残すことが連想されると思います。
しかし上記のような遺言はもちろん故人にとって気がかりで大事なことであることには違いありませんし、遺訓として残された人に道義上や心理上の影響を与えますが、法的効果のある遺言とは異なります。
法律上の遺言とは、民法で定められた形式・要件に従って作成されたものを指し、遺言で定めることの内容も民法に規定されていることに限られます。
せっかく遺言を作成しても、この形式、要件、内容が法律に合致していないと無効となります。
遺言はご家族や親しい人への最後のメッセージとなるものです。 きちんと最後の思いを実現できるよう当事務所では、遺言作成のお手伝いをいたします。お気軽にご相談ください。
遺言書作成の要件
- 遺言作成時に遺言能力があること
-
満15歳未満、成年被後見人、心神喪失状態の場合は遺言作成ができません。
(成年被後見人の場合は、本心に復している時は医師2名の立会いのもと遺言を作成することができます。) - 民法で定められた遺言の形式に従っていること
- 普通方式(自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言)、特別方式のいずれかの要件を満たしている。
- 遺言の内容が民法に規定された内容であること
遺言書で定めることのできること
-
相続人の廃除、または廃除の取り消し
➡ 相続人の廃除とは被相続人を虐待するなどした相続人から相続権を失わせる手続きです。 - 子の認知
- 財産の遺贈
- 財団法人設立のための寄付行為
- 信託の設定
- 遺言執行者の指定・指定の委託
➡ 遺言執行者は遺言の執行など様々な相続手続きの一切を単独で行うことができます。 - 遺贈に関する遺留分減殺方法の指定
- 遺産分割の方法の指定・指定の委託
- 遺産分割の禁止(最長5年まで)
- 相続人の担保責任の指定
- 相続分の指定、指定の委託
- 未成年後見人、未成年後見監督人の指定
普通方式遺言の比較
| 作成の手順 |
■ 全文を自筆で書く ■ 日付を自分で書く ■ 氏名を自分で書く ■ 押印する |
|---|---|
| 家庭裁判所の検認 | 必要※ |
| 保管 | 自分で管理 |
| メリット |
■ 費用が安価 ■ 遺言を作成したことを秘密にできる ■ 簡単に作成できる |
| デメリット |
■ 内容・形式の不備により無効となる恐れがある ■ 紛失の恐れがある ■ 偽造・変造の恐れがある ■ 検認手続きが必要 |
| 作成の手順 |
■ 遺言者が遺言を作成・押印・封印のうえ、公証人に遺言者が作成したものであることを確認してもらう ■ 証人2名が作成時に立ち会う |
|---|---|
| 家庭裁判所の検認 | 必要※ |
| 保管 | 自分で管理 |
| メリット |
■ 遺言の内容を秘密にできる ■ 偽造・変造を防げる ■ ワープロ使用可(署名・押印は必要) |
| デメリット |
■ 内容・形式の不備により無効となる恐れがある ■ 紛失の恐れがある ■ 作成に費用と手間がかかる ■ 検認手続きが必要 |
| 作成の手順 |
■ 遺言者が公証人に内容を伝え、公証人が公正証書を作成する ■ 証人2名が作成時に立ち会う |
|---|---|
| 家庭裁判所の検認 | 不要 |
| 保管 | 公正役場で保管 |
| メリット |
■ 専門家作成のため形式等は事前にチェック済み ■ 保管の心配がない ■ 偽造・変造を防げる ■ 検認不要のためすぐに使える |
| デメリット | ■ 作成に費用と手間がかかる |
上記のメリット・デメリットを勘案した結果、当事務所では公正証書遺言の作成をお勧めいたします。
※裁判所の検認を経ないで開封する等の行為をすると過料が科されるので注意
遺言書の作成をお勧めする事例
子供のいない夫婦の場合(妻又は夫に全財産を残したい)
子供(直系卑属)がいない場合の相続人は、その配偶者と親(直系尊属)又は兄弟姉妹が相続人となります。
遺産分割協議は相続人全員が参加する必要がありますが、例えば故人の妻と故人の兄弟が相続人となった場合は、相続人間には血の繋がりがなく交流があまり無いということは珍しくありません。
このような場合協議が難航することが予想されますが、遺言を作成しておけばそのような問題は未然に防げます。
なお、兄弟姉妹の相続人には遺留分がないので、遺言の内容に反するような主張をすることはできません。
相続人以外にも財産を譲りたい
相続人以外には遺言で定めない限り財産を与えることはできません。
生前特にお世話になった人、配偶者の連れ子など相続権の無い人に財産を与えたいとお考えなら遺言の作成が必要です。
推定相続人に行方不明者や認知症の疑いのある方がいる
遺産分割協議をするには相続人全員が参加する必要があります。
この例の場合、行方不明や認知症で協議に参加ができないからといって協議から除外することはできません。
有効な遺産分割協議をするには行方不明の場合は不在者財産管理人、認知症などで判断力に問題があるようなら成年後見人の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります。
これらの手続きには費用や時間がかかりますが、あらかじめ遺言によって遺産分割を定めておけば円滑に手続きを進めることができます。
公正証書遺言作成手続きの流れ
当事務所で遺言書作成をご依頼いただいた場合の手続きは下記の手順で進んでいきます。
-
- 1.相談
-
相続財産・相続人など必要事項を聴取しながら、依頼者のご希望にそった内容になるようご相談を受けます。
※相続税の申告が必要と予想される場合、税理士と協力しながら遺言内容を検討します。
-
- 2.必要書類の手配
- 戸籍謄本、住民票、登記事項証明書(登記簿謄本)、固定資産評価証明書など必要となる書類を集めます。
-
- 3.公証人との打ち合わせ
- 遺言の内容等について公証人と事前に打ち合わせをして、公正証書作成の日時を決めます。
依頼者が公証人の出張を希望していれば、出張場所も打ち合わせします。
-
- 4.公正証書遺言の作成
- 公証役場又は出張先において公正証書遺言を作成します。必要な証人については、当事務所で手配できます。
(推定相続人は証人になれないので、依頼者が手配するのは結構面倒です。)
遺言書作成に関する諸費用については、後見業務・遺言書作成に関する費用をご覧ください。
後見

既に高齢化社会と言われて久しく、平均寿命も昔と比べて長くなっております。
長生きは誰もが望むものの、判断力が衰えた場合のことを考えると不安になる人は多いと思います。
そこで判断力の衰えに応じて国は後見・保佐・補助の制度を定めました。 皆様が安心して老後の生活を送れるようお手伝いをしたいと思い、後見業務に取り組んでいきます。
法定後見制度
法定後見制度は、本人の判断力の状態に応じて、成年後見・保佐・補助の3つの類型に分けられます。
判断力の低下が最も重い場合は成年後見、中程度が保佐、最も症状が軽い場合は補助となります。
また、後見人等の権限も成年後見人が最も大きく、保佐人は中程度、補助人は最も小さくなります。
このように本人の判断力の状態が重要な要素であるため、申立には必ず医師の診断書が必要です。
申立の際に後見人等の候補者を挙げることはできますが、最終的には家庭裁判所が選任するため必ずしも候補者が選任されるとは限りません。
親族間に争いがある場合は、親族の候補者を避け、司法書士・弁護士などが選任されることがあるようです。
申立には、申立書のほか、医師の診断書、戸籍などの身分関係書類、預金通帳など財産関係書類など多数の書類が必要となります。
申立のあと医師の鑑定を行うので、選任まで通常3ヶ月ほどかかりますが、症状が重篤で明らかに判断力を喪失している場合は鑑定が省略され1ヶ月くらいになります。
なお、居住用不動産の売却を行う場合には、後見人の選任だけでなく、居住用不動産の処分につき家庭裁判所の許可が必要なので時間がさらにかかります。
任意後見契約
判断力が衰える将来に備えて本人と後見人候補者が公正証書で任意後見契約を締結します。本人のライフプランに応じて具体的にどのようなことを後見人が行うかが契約の内容になります。
任意後見契約は、本人が後見人候補者に対し契約の効力発生の意思表示を行い、任意後見監督人が家庭裁判所から選任されることによって始まるのが一般的です。
当事務所では、将来の計画を立てるという点から任意後見契約締結の際には、遺言書も併せて作成することをお勧めしています。
見守り契約
見守り契約とは、任意後見契約締結から効力発生まで定期的に後見人候補者が本人に連絡や面談をすることにより、健康状態や近況の把握をする契約です。
任意後見契約では、契約締結から効力発生まで相当の期間がかかるのが普通です。契約締結後に全く本人と候補者が連絡を取らないのでは互いに信頼関係を維持することが難しいことからこのような契約により関係維持を図ります。
見守り契約は任意後見契約自体に盛り込むことも可能ですし、任意後見契約締結後に別途締結してもかまいません。
見守り契約は公正証書による必要はありません。
見守り契約は、事務負担がそれほど重くないことから報酬も低額であることが普通です。
任意代理契約(身上監護・財産管理)
代理契約自体は成年後見以外にも通常行われている契約です。
後見(法定・任意)は本人の判断力が不十分な場合に適用されるものですので、判断力に問題が無いが身体が衰えている人には適用がありません。
しかし判断力に問題が無くても車椅子を使用して歩行困難である場合など、後見人が行うような業務を依頼したいという事例は珍しいことではありません。
そこで判断力が低下する前から身上監護・財産管理などを委任したいという場合に、任意後見契約と併せて任意代理契約を締結します。
代理契約自体は通常の契約なので公正証書による必要はありませんが、委任する権限が大きくきちんと内容を定めないと本人を害する恐れがあるので、当事務所では任意後見契約とセットか別途公正証書による契約締結をお勧めします。
時系列でみる後見・遺言・相続手続き
-
- 1.「任意後見契約」「遺言書作成」
-
- 2.「見守り契約」
「任意代理契約による財産管理・身上監護」
- 2.「見守り契約」
-
- 3.「判断力低下」
-
- 4.「任意後見・法定後見による財産管理・身上監護」
-
- 5.「死亡」
-
- 6.「後見終了手続き」「相続手続(遺言執行)」
遺言 / 後見の費用はこちら>
アクセス
- 所在地
- 〒184-0004 東京都小金井市本町5丁目3番24号 関ビル1階
JR中央線 武蔵小金井駅 北口から徒歩5分