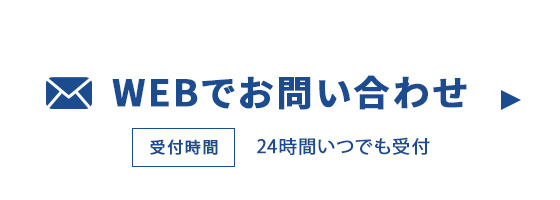後見人とは、判断能力が不十分な人(被後見人)の財産管理や生活支援を法的に行う役割を担う人を指します。後見人は、家庭裁判所により任命され、被後見人の利益を最優先に考えて行動します。後見人制度は、特に高齢者や未成年者、障害を持つ人々が安心して生活できる環境を整えるために重要です。
本記事では、後見人の具体的な職務内容、メリット・デメリット、注意点などについて詳しく説明します。
成年後見制度の種類:法定後見制度と任意後見制度
成年後見制度には、大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。それぞれの制度について、詳しく見ていきましょう。
法定後見制度:3つの類型
法定後見制度は、すでに判断能力が不十分な状態になった方を対象とした制度です。この制度は、本人の判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの類型に分かれています。家庭裁判所に申立てを行い、家庭裁判所が本人の判断能力を審査した上で、適切な類型を決定します。
これらの類型は、本人の判断能力の程度に応じて選択されるため、本人の自己決定権を尊重しつつ、必要な支援を提供することができます。
後見
判断能力が欠けているのが通常の状態にある方を対象としています。例えば、重度の認知症や知的障害のある方が該当します。後見人は、本人の財産管理や契約などの法律行為全般について代理権を持ちます。また、本人が行った法律行為は、後見人が取り消すことができます。
保佐
判断能力が著しく不十分な方を対象としています。軽度から中度の認知症や知的障害のある方が該当することが多いです。保佐人は、民法で定められた重要な法律行為(借金、訴訟行為、不動産の売買など)について、同意する権限を持ちます。また、家庭裁判所の審判により、特定の法律行為について代理権を与えられることもあります。
補助
判断能力が不十分な方を対象としています。軽度の認知症や知的障害のある方が該当することが多いです。補助人の権限は、本人の同意を得た上で、家庭裁判所が定めた特定の法律行為に限定されます。
任意後見制度:将来に備えた契約
任意後見制度は、将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自分で後見人を選び、その人に代理権を与える契約を結んでおく制度です。この制度は、本人の判断能力があるうちに、公正証書で任意後見契約を結びます。そして、将来、本人の判断能力が低下した際に、任意後見人が家庭裁判所に申立てを行い、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することで、契約の効力が生じます。
任意後見制度のメリットは、自分で信頼できる人を後見人に選べることと、後見人の権限を細かく設定できることです。例えば、財産管理だけでなく、医療や介護に関する決定権を与えることもできます。
また、自分の意思や価値観を尊重した後見活動を期待することができます。
成年後見制度利用の手続き
成年後見制度を利用する際の手続きについて、具体的に説明しましょう。
法定後見制度の場合
まず、家庭裁判所に後見開始の審判を申し立てます。申立ては本人、配偶者、四親等内の親族、市区町村長などが行うことができます。申立ての際には、本人の戸籍謄本、住民票、診断書などの書類が必要です。家庭裁判所は、本人の判断能力を審査し、適切な類型(後見、保佐、補助)を決定します。そして、ふさわしい後見人等を選任します。
後見人等には、親族が選ばれることもありますが、本人の財産管理や身上保護を適切に行える人物が選ばれます。近年では、弁護士や司法書士などの専門職が後見人等に選任されるケースも増えています。専門職後見人は、法律や財産管理の知識を活かして、適切な後見活動を行うことができます。
任意後見制度の場合
まず公証役場で任意後見契約を結びます。この契約は公正証書で作成する必要があります。契約では、任意後見人の権限や報酬などを細かく定めます。そして、本人の判断能力が低下した際に、任意後見人が家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行います。家庭裁判所が任意後見監督人を選任することで、任意後見契約の効力が生じます。
後見人の基本的な役割
後見人の基本的な役割は、本人の利益を守り、その生活を支援することです。主な役割は以下の通りです。
後見人は、これらの役割を果たす際に、常に本人の最善の利益を考え、誠実に職務を遂行する必要があります。また、本人の自己決定権を尊重し、可能な限り本人の意思を反映させることが求められます。
財産管理
本人の財産を適切に管理し、必要な支出を行います。具体的には、預貯金の管理、不動産の管理、各種支払いの手続きなどを行います。
後見人は、本人の財産を適切に把握し、適正に管理する義務があります。
身上保護
本人の生活や健康、福祉に関する事務を行います。例えば、介護サービスの契約、医療機関への入退院の手続き、施設入所の契約などを行います。
後見人は、本人の生活の質を維持・向上させるために、適切なサービスを選択し、契約を行います。
法律行為の代理
本人に代わって契約を締結したり、各種手続きを行ったりします。例えば、不動産の売買契約や賃貸契約、保険金の請求などを行います。後見人は、本人の利益を最大限に考慮しながら、これらの法律行為を行う必要があります。
本人の意思尊重
後見人は、可能な限り本人の意思を尊重し、本人の希望や価値観に沿った支援を行う必要があります。本人の意思を確認することが難しい場合でも、本人の過去の言動や生活歴を考慮して、本人の意思を推定するよう努めなければなりません。
定期的な報告
後見人は、定期的に家庭裁判所に後見事務の報告を行う義務があります。この報告により、後見人の活動が適切に行われているかが確認されます。報告には、財産管理の状況や身上監護の内容などを記載します。
成年後見制度のメリット・デメリット
成年後見制度には、様々なメリットとデメリットがあります。制度の利用を検討する際は、これらを十分に理解しておくことが重要です。
メリット
- 財産管理の適正化:後見人が本人の財産を適切に管理することで、財産の散逸や不正利用を防ぐことができます。特に認知症の方の場合、悪質な勧誘や詐欺から財産を守ることができます。
- 法律行為の代理:本人に代わって契約や手続きを行うことができるため、必要なサービスの利用や権利の行使が可能になります。例えば、介護サービスの契約や年金の受給手続きなどを円滑に行うことができます。
- 身上保護の充実:後見人が本人の生活や健康に配慮した支援を行うことで、本人の生活の質を維持・向上させることができます。適切な医療・介護サービスの選択や、生活環境の整備などが可能になります。
- 本人の意思の尊重:特に任意後見制度では、本人が信頼する人を後見人に選び、自分の意思や価値観を尊重した支援を受けることができます。
- 虐待や搾取からの保護:後見人が本人の権利擁護者として機能することで、家族や第三者からの虐待や搾取を防ぐことができます。財産管理の適正化:後見人が本人の財産を適切に管理することで、財産の散逸や不正利用を防ぐことができます。特に認知症の方の場合、悪質な勧誘や詐欺から財産を守ることができます。
デメリット
- 本人の行為能力の制限:特に成年後見の場合、本人の法律行為が制限されるため、自由な財産処分ができなくなる可能性があります。
- 費用負担:後見人の報酬や手続きにかかる費用など、経済的な負担が生じます。本人の財産から支払われるため、財産が少ない場合は負担が大きくなる可能性があります。
- 後見人との関係:後見人と本人の関係が良好でない場合、支援がうまくいかない可能性があります。特に親族が後見人になる場合、家族関係に影響を与えることもあります。
- 柔軟性の欠如:法定後見制度では、一度開始すると終了するまで継続するため、本人の判断能力が回復した場合でも即座に制度を終了することは難しいです。
これらのメリット・デメリットを踏まえた上で、個々の状況に応じて制度の利用を検討することが重要です。
成年後見制度の注意点
成年後見制度には、いくつかの注意点があります。
権限に制限がある
後見人等の権限には制限があり、本人の居所の指定や、医療行為の同意など、本人の人格に深くかかわる事項については、原則として後見人等に決定権がありません。
費用がかかる
後見人等の報酬や手続きにかかる費用など、経済的な負担も考慮する必要があります。
責任が伴う
後見人には、善管注意義務や忠実義務が課せられており、本人の利益のために誠実に職務を遂行しなければなりません。後見人が不適切な行為を行った場合、家庭裁判所による解任や、場合によっては法的責任を問われる可能性もあります。
まとめ
後見人とは、判断能力が不十分な人(被後見人)の財産管理や生活支援を法的に行う役割を担う人です。後見人は家庭裁判所により任命され、被後見人の利益を最優先に考えて行動します。
成年後見人制度を利用することで、高齢者や未成年者、障害を持つ人々が安心して生活できる環境を整えることができます。
成年後見人制度の利用を検討する際は、専門家のアドバイスを受けることが非常に重要です。司法書士法人アクセス総合事務所では、豊富な経験と専門知識を持つ専門家が、お客様の状況に応じた最適な対策をご提案いたします。
早めの準備と適切な対策が、将来の安心につながります。ぜひ、アクセス総合事務所にご相談いただき、ご家族の未来を守るために一緒に考えていきましょう。