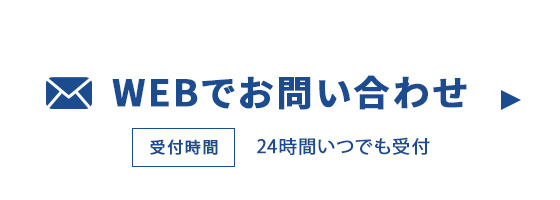終活とは、自分が亡くなった後のことを考え、残された家族が困らないよう、事前に準備をしておく活動です。現代、スマホなどにより自分の意思を残しやすくなり、終活をより身近に考える方が増えています。
終活には医療や介護、葬儀に関することなども含まれますが、今回は「遺産相続」においてすべきことをご紹介します。
終活を考えているという方は、是非参考にしてみてください。
相続に関する終活をするメリット
相続に関する終活を行うことで、様々なメリットが得られます。事前に適切な準備や対策を講じることで、相続に関する多くの問題を未然に防ぎ、スムーズな財産の引き継ぎが可能となります。
トラブルを防止できる
相続手続きにおいて最も頻繁に発生するトラブルは、相続人同士の争いです。被相続人(故人)が生前に相続に関する終活を行うことで、このようなトラブルを効果的に防ぐことができます。具体的な遺産分割の方法や相続人の指定を事前に決めておくことで、相続人(財産を相続する権利を持つ人)の間での意見の相違や対立を避けることができます。また、相続人の負担も大幅に軽減されるため、悲しみの中にある家族が不必要な争いに巻き込まれることなく、故人の遺志を尊重しながら相続手続きを進めることができます。
相続税を軽減できる
生きているうちに計画的に対策をしておくことで、相続税を大幅に軽減することが可能です。相続税の対策は複雑で専門的な知識が必要ですが、相続対策は早ければ早いほど効果的な方法を見出すことができます。どの財産をどのような方法で対策すれば良いか、今のうちから確認し、考えておくことが大切です。例えば、生前贈与の活用や不動産の評価方法の見直し、また相続時精算課税制度の利用など、様々な方法があります。これらの対策を適切に行うことで、相続人の税負担を軽減し、より多くの財産を次世代に引き継ぐことができます。
財産が整理できる
財産目録を作成することで、全ての財産を把握し、適切に管理することができます。これは、被相続人自身の財産管理に役立つだけでなく、相続人が遺産をスムーズに引き継ぐ際にも非常に重要です。財産目録には、不動産、預貯金、有価証券、生命保険、貴金属、美術品、自動車などの資産だけでなく、借入金などの負債も含めて詳細に記載します。この作業を通じて、自身の財産状況を明確に理解し、より良い資産運用や相続対策を立てることができます。また、相続人にとっても、被相続人の財産全体を正確に把握できるため、遺産分割の話し合いがスムーズに進み、相続手続きにかかる時間と労力を大幅に削減することができます。
相続に関して、終活ですべきこと
それでは、詳細にはどのようなことを終活で行えば良いのでしょうか?
遺言書の作成
遺言書は、自分の死後に財産をどのように分配するかを明確に示す法的な文書です。遺言書を作成することで、相続人の争いを防ぐことで相続手続きを円滑に進めつつ、自分の意思を確実に反映させることができます。
相続に関して、遺言書に記すべき内容は以下です。
財産の分配方法
各相続人に対して具体的にどの財産をどのように分配するかを明示します。
「長男に自宅を相続させる」「次男に預貯金を相続させる」「長女に株式を相続させる」といった具体的な指示を記載することも可能です。
ただし、いくら指示ができるといっても、相続人の誰が見ても納得のできるように配慮をすることも大切です。「○○をしてくれて感謝をしているから」「○○してあげられなかったから」などのように理由をつけることで、相続人の理解も得られやすくなります。
遺言執行者の指定
遺言執行者とは、遺言の内容を実行しながら相続手続きを行う者のことです。
兄弟や親族が大勢いる場合、話し合いが難航してしまう可能性がありますが、責任者を指定することで意見がまとまりやすくなります。
遺言執行者には、未成年や破産者以外なら誰でも指定することができます。
弁護士や司法書士などの専門家を指定することもできるため、よりスムーズに相続手続きを行いたい、土地や不動産などのように財産が多くあるという場合、専門家を指定することもおすすめです。
また、遺言書は作成方法に問題があると無効になってしまう可能性があります。
よって、以下のことを遵守しながら作成してください。
- 署名や押印をする:遺言書を作成した本人の署名や押印がないと、原則として無効になってしまいます。
- 日付を明記する:遺言書を作成した日付が明記されていないと、原則として無効になってしまいます。○年○月○日まで、詳細に明記しなければいけません。
- 内容は具体的にする:曖昧な表記をしてしまうと、無効となってしまう可能性があります。例えば、「不動産を長男に相続する」と記した場合、どの不動産のことを示しているのかがわかりません。よって、住所まで記したうえで指示する必要があります。同様の例だと、銀行や株式、負債などがあります。
遺言書の作成方法で不安な点がある場合、専門家に相談することをおすすめします。
財産目録の作成
財産目録は、自分の全財産をリストアップしたもので、相続人が遺産の全体像を把握するのに役立ちます。財産目録を作成することで、遺産分割がスムーズに進み、見落としや誤解を防ぐことができます。
以下を確認して、財産の漏れがないようにしておきましょう。
【相続の対象となる財産】
- 不動産:土地や建物など
- 預貯金:銀行口座の残高
- 有価証券:株式、債券、投資信託など
- 動産:自動車、宝石、骨董品など
- 保険金:生命保険の死亡保険金
- その他の財産:著作権や特許権などの知的財産権
また、プラスの財産だけでなく、住宅ローンや未払いの医療費など、マイナスの財産についても記しておく必要があります。
生前贈与を活用する
生前贈与とは、生きているうちに自分の財産を贈与することです。結果的に、死後の手続きの負担を減らすことができます。
生前贈与のメリットとしては、相続税の負担を軽減することができます。特に年間110万円までの贈与は非課税となるため、うまく活用することで財産を効率的に移転できます。
注意点としては、贈与税の申告や非課税枠の確認を怠らないようにすることが必要です。贈与契約書を作成し、税務署に申告することで非課税枠を活用できます。
相続税の対策
相続に相続税がかかることはご存知かと思いますが、以下のような方法で相続税を軽減することが可能です。
生命保険を活用する
生命保険金には、「500万円 × 法定相続人の数」までの非課税枠があります。この非課税枠を活用することで、相続税の負担を軽減することができます。
小規模宅地等の特例
被相続人が居住していた宅地や事業用の宅地については、一定の要件を満たせば、評価額を最大80%減額できる特例があります。
財産評価の見直し
不動産や非上場株式の評価額を適切に見直すことで、相続税の課税額を抑えることができます。専門家の助言を受けて正確な評価を行いましょう。
専門家に相談してスムーズな終活を
相続対策は複雑で専門的知識を要するため、専門家のサポートを受けることをおすすめします。弁護士、税理士、司法書士などの専門家は、個々の状況に応じた最適な相続税対策の提案や、財産評価方法、特例適用条件など、具体的なアドバイスを提供してくれます。
例えば、司法書士法人アクセス総合事務所では、相続に関する幅広い相談に対応しています。遺言書作成のサポート、相続手続きの流れや必要書類の説明など、経験豊富な専門家が丁寧にサポートしてくれます。早めに専門家に相談することで、自分の状況に合った最適な終活や相続対策を立てることができ、将来の不安を解消し、円滑な相続につなげることができるでしょう。
終活は、自分自身のためだけでなく、大切な家族のためでもあります。この記事を参考に、ぜひ早めの準備を始めてみてください。適切な終活により、自分の意思を尊重しつつ、残された家族の負担を軽減し、円満な相続を実現することができるでしょう。